簪(かんざし)に関して
和装の時に使うヘアアクセサリーといえば「簪:かんざし」ですね。
このかんざしにも非常に豊富な種類があり、伝統的なものから流行りまで様々です。
かんざしとは
かんざしの原点は、なんと縄文時代にまでさかのぼります。古来先の尖った1本棒には、呪力が宿ると信じられていたそうです。
そこで髪に1本の棒を指すことによって魔除けできると考えられたのが始まりです。
奈良時代には中国文化の影響で、男女問わずかんざしをさし髪を結っていたようです。その後平安時代は髪をおろし髪そのものの美しさを求めた時代になります。かんざしを使うことはなくなり、江戸時代になって復活します。
江戸時代後期から豊富は種類の髪飾りが使われ始めました。木や象牙、べっ甲や馬爪など。ガラス製のものもあったようです。
特に遊女のかんざしは豪華で美しく飾られていました。
かんざしの種類
玉かんざし・・・
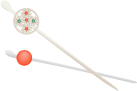
平打かんざし・・・

つまみかんざし・・・

小さくカットした布を折りたたみ、土台に貼り付けて幾重にも重ねて花を表現したかんざしを総称してつまみかんざしといいます。花かんざしとも呼ばれ、素材は正絹が基本です。
チリカン・・・

ビラカン・・・
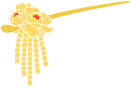
金属製のセンスや丸い形をしていて、家紋がほどこされています。舞妓が前差しとして使います。
他にも、松葉かんざし・吉丁・びらびらかんざし・鹿の子留め・両天かんざし・くす玉などがあります。
現在ではあまり使われていないかんざしもありますが、時代によって様々な流行りがあったようですね。
現在はラインストーンを使うなど、カジュアルなかんざしがたくさんあります。
和装だけでなく洋装でもかんざしが取り入れられています。
素材でかんざしを選ぶのもいいですね。銀製・漆塗り・べっ甲・象牙・珊瑚など。
形で選ぶなら、1本かんざし・2本かんざし・くし型・おうぎ形などがあります。
伝統的なかんざしを選ぶなら、京七宝や漆器などもいいでしょう。